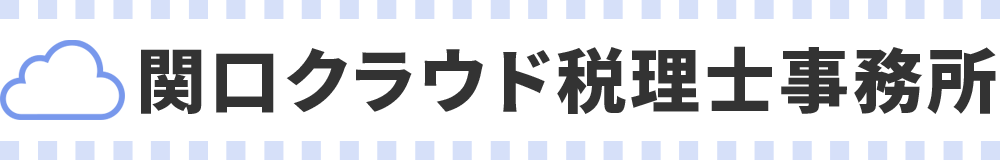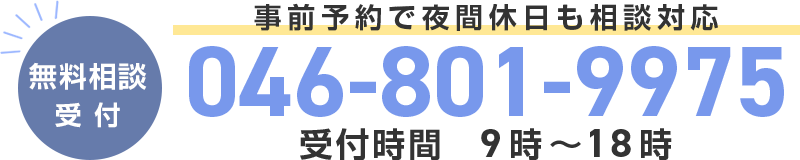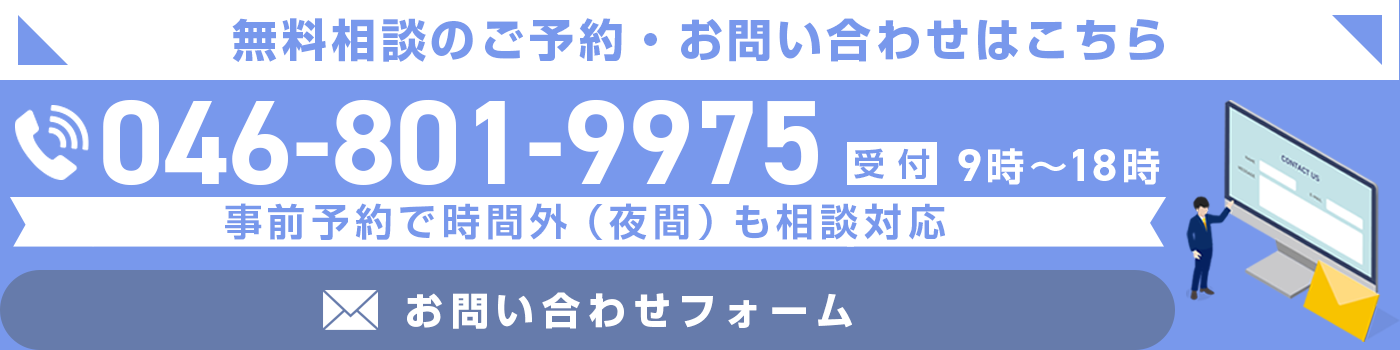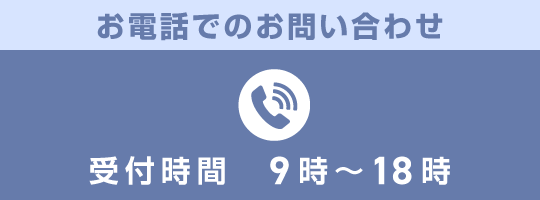このページの目次
「確定申告」とは
確定申告とは、前年1月1日から12月31日までの1年間の収入と経費を差し引いて所得を計算し、確定申告することです。例えば、令和6年1月1日から12月31日の1年間の令和6年分は、令和7年3月17日(令和7年3月15日は土曜日だったため)までが確定申告の期間になります。自営業、フリーランスや家賃収入がある人は、基本的に毎年確定申告を行う必要があります。
会社員や公務員の人は、勤務先で年末に生命保険料控除の証明書や家族の扶養状況を会社に提出することで「年末調整」を行います。
年末調整を行った際、源泉徴収が多すぎた場合、12月や1月の給料で返ってくるため、会社で年末調整してもらっているので基本的に確定申告は不要です。
しかし、年末調整の資料提出の締切りに間に合わなかった分や、医療費控除など年末調整ではできないものは確定申告しないと税金を取り戻せません。
ケース別にみていきましょう。
1.勤務先の年末調整に間に合わなかった場合や提出し忘れた場合
早い会社だと11月初旬までに年末調整の書類の提出を求められます。しかし、その後に年末調整の書類が届いたり出し忘れていた場合です。確定申告を提出すれば、控除を受けることができます。年末に結婚した場合や子どもが生まれたとき場合も年末調整しないと控除額が大きいので注意しましょう。また、別居している親に相当の金額を送金している場合も控除額を受けれる場合があるので注意しましょう。
最近の場合、年末調整の書類を出し忘れて基礎控除を受けていなかったということもあるので注意してください。
2.年末調整では手続きできないケース
勤務先に提出する年末調整の書類に記載欄がない控除は、自分で確定申告する必要があります。「雑損控除」、「医療費控除」、「寄付金控除」です。
- 雑損控除…火災、水害などの災害や盗難などにあった場合に受けられる控除
- 医療費控除…自分と家族の医療費を10万円以上支払った場合受けられる控除
※医療費控除を受ける年の所得金額が200万円未満の人は、支払った医療費から所得金額の5パーセントの金額を差し引いた金額になります。
- 寄附金控除…ふるさと納税など特定の市町村・団体に寄付した場合の控除
※ふるさと納税はワンストップ特例を利用した場合、確定申告は不要です。しかし、医療費控除など確定申告することになった場合は、ワンストップ特例は無効になり、ふるさと納税の分も合わせて確定申告書に記載しないといけないので注意してください。
「医療費控除」は、領収書をもらった金額だけでなく、往復の交通費も加算できます。ただし基本的にタクシー代や自家用車の駐車場代、ガソリン代は含めることはできません(やむを得ずタクシーを利用せざるを得ない場合は対象になることもあります)。公共交通機関の運賃のみですが、計算してみると大きな金額になります。
また、補てん金などの生命保険金を受け取った場合は、その金額分は控除できませんので注意しましょう。
まとめ
年末調整で提出し忘れていた場合などは、その年分について確定申告書を提出することができる場合があります。対象になる年の翌年1月1日から5年間提出することができるので、この5年間で提出し忘れてなかったか確認してみましょう。
確定申告の必要がない方(自営業や家賃収入がある人以外など)の還付申告は、還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間行うことができます。例えば、令和2年分の確定申告をしていなかった場合、令和7年12月31日まで申告することができます。同様に、令和6年分については、令和7年1月1日から令和11年12月31日まで申告することができます。

国税の現場で約33年間、幅広い業種の調査や審査に携わってきた経験を活かし、「関口クラウド税理士事務所」を開業しました。
相続税の申告や確定申告、税務調査など、日常の税務のお悩みからイレギュラーな対応まで、丁寧にお応えしています。
横浜・横須賀・三浦を拠点に、全国のお客様とオンラインでつながり、ZOOMやLINEを活用して、距離を感じさせない対応を心がけています。
クラウド会計を導入し、北海道から沖縄までスムーズにご対応可能です。
初回相談は無料、事前にご予約いただければ夜間や休日の対応も承ります。身近な相談相手として、どうぞお気軽にご連絡ください。